本日の午前と午後は、「サロン」と「法話会」に行ってきました。
毎年この時期に寄せていただくH地区のサロンは、今年で3回目となります。
このH地区は、「男女の比率がほぼ同じ」という、大変すばらしい地区です。
ほとんどの地区のサロンでは、男性の比率は一割ほどですので、うれしいかぎりでした。

ネッ 男性の方が多いでしょ
また、たいていは「歌」や「手遊び」をしても、男性の方は消極的で、ノリも今ひとつなのです。
このことは、「女性の寿命が男性よりも長い理由のひとつ」かも知れませんね。
しかし、こちらのH地区の男性は、とてもノリがよく、積極的に参加してくださいます。
歌を歌うとコーラスになって、素敵に聞こえてきます。思わず「合唱団を結成されては」と、お薦めしてしまったほどです。
私も3回目のサロンなので、「新しい出し物を」と頭をひねって工作をするのですが、いつもギリギリになって追い込まれないと本腰が入らない私なので、自分でも冷や冷やです。
今回は、新しい出し物を2つ用意しました。ひとつはそれなりにうけましたが、もうひとつはいまいちでした。
すこし高度(?)すぎたのかもしれません。
(アア~嫌だ 素直になれない ワ・タ・シ・)
今一度、出し物を練り直さなくっちゃ。
切ったり、貼ったり、書いたり、縫ったり………。
園児の工作のようなものを「ああでもない」、「ウーンこうでもない」とやっている私を、住職がいつも冷やかに「幸せやなあ~、大したもんやあ~」と、かっちゃま弁で冷やかすのです。
私は、「遊びじゃないのよ、真剣なのよ」と言いながら、「ほーんとにそうかも」と思っています。
皆さんへ笑いを提供できることが、私の原動力かも知れません。H地区の皆さん、今日もお付き合い有り難うございました。
法話会では、最近出会ったお話をしました。「いのちを いただく(内田美智子作)」というお話です。
最近、とみに涙もろくなり、話す私自身が感極まって、ついつい涙してしまうのです。
姫の目にも涙? ひえっ! 姫ってもしかして~~
深く追求しないでください。
追伸:先日、歌手の島倉千代子さんが言われていました。
「東京だよ、おっかさん」を歌いながら、自分の方が泣けてきて
つい涙声で歌っていると、船村徹先生に叱られた。
こちらから涙の押し売りをしてどうする!
聞き手が、それぞれのおっかさんを
思い浮かべてもらうのが、歌手の仕事だ!
と言われたと、話しておられました。
エッ? 比較が違う! はい、すいません。 
素直に認める、かよわい シ~子姫 でした。

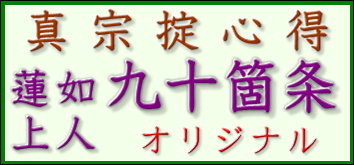
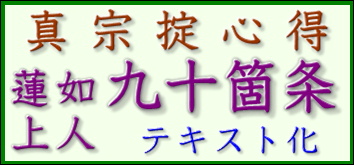




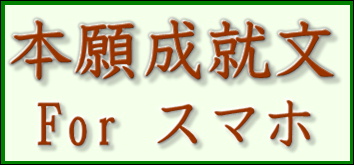
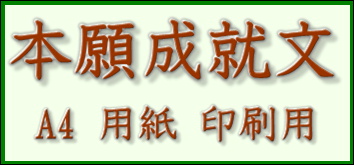
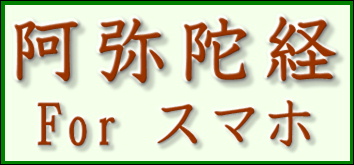































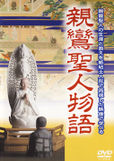
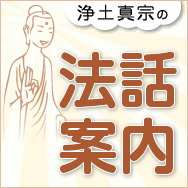
最近のコメント