越前そば道場
本日、全国で最初に誕生した「越前そば道場」へ行って来ました。
こちらの「そば打ち道場」は、福井市内にある豪邸です。もう20数年も前から道場を開いておられたのですが、今回、不思議なご縁で初めて寄せていただきました。
当主の中山重成さんは、県内で幅広く飲食店を経営する企業の会長でもあり、福井のそば文化に造詣の深い『そば博士』でもあるのです。
初めての訪問なのですが、有り難いことに、そんな中山さんより色々なお話しをお聞かせいただくことができました。
中山さんは、2007年(平成19年)に米寿を迎えられ、ご高齢でいらっしゃるのにすごくお元気で、常に将来のことを考えておられるようです。
この道場を創設されたのは、「福井の文化でもある越前そばを全国に広めたい」との思いからだそうです。
そして、1985年(昭和60年)に中山さんが、全国初の「そば道場」を福井に創設されてからは、全国にそば打ち道場が広がり、そば打ち愛好家は現在も増加中です。
そんな中山さんの功績により、1996年(平成8年)からは福井で『全日本素人そば打ち名人大会』が開催されるようになり、今や福井は「そば打ち愛好家の聖地」とまでも呼ばれるほどになりました。
福井のそばを全国的に有名にした中山さんは、今年で16回目となる『全日本素人そば打ち名人大会』の審査委員長もされています。
2階の部屋には、第1回から第15回目までの「歴代のそば打ち名人の写真」が掛けられてありました。
そんな中山さんの「そば道場」へは、創設当初から全国各地より著名な方々がたくさん訪れ、そば打ちを楽しんでいます。
豪華な部屋には、故佐藤栄作元首相、元横綱の千代の富士など、政財界や芸能界の有名人が、そばを打っている写真も飾ってありました。
玄関には、数本の「蕎麦棒(麺打ち道具のひとつ)」が飾ってあり、アメリカの大リーグで活躍するイチロー選手や、松井秀喜選手が使用しているバットと同じ材質で出来ているそうです。
当主の中山さんとの語り合いは、蕎麦談義ばかりでなく、仏法のことについてまでも及び、「できれば蕎麦だけでなく、この道場を心のよりどころになるような場にしていきたい」と仰いました。
また、中山さんは、「今までこうして生かされて来たのは、多くの方々のおかげであり、その喜びを少しでも多くの方々におすそ分けしたい」とも仰っておられました。
中山さんは、過去に多くの福祉事業にも貢献されておられるようです。
短い時間ではありましたが、貴重なものと多くのことを学びました。
中山さん、お忙しい中、本当に有り難うございました。また寄せていただきます。

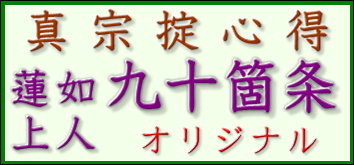
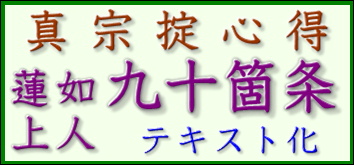




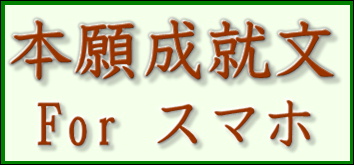
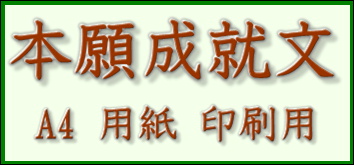
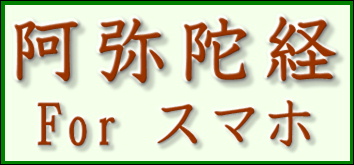










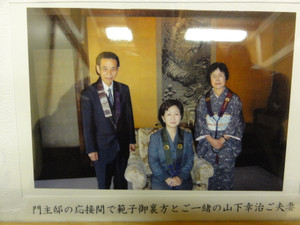




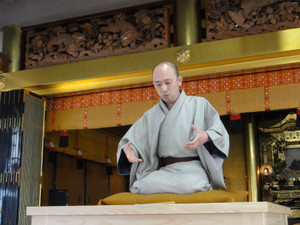


















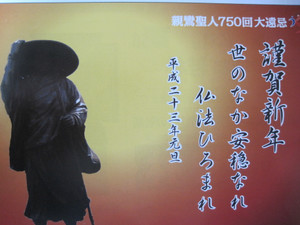
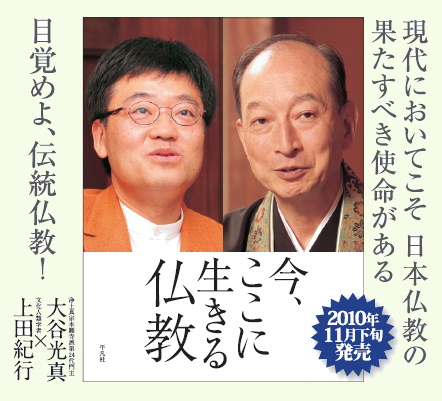
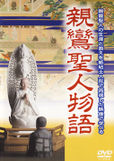
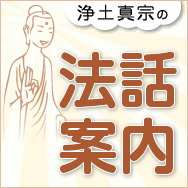
最近のコメント